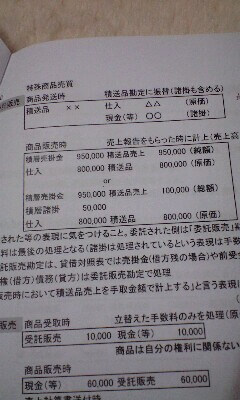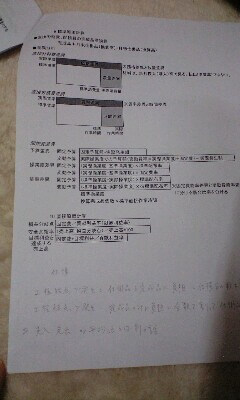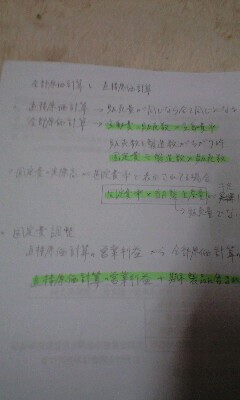教材も恋愛も「浮気」は良くない!自分の選択を最後まで信じよう!
- 投稿者:まー蔵さん
- 勉強形態:独学
- 受験回数:1回
- 勉強期間:約5か月
日商簿記検定2級を受験するきっかけ
第122回の3級受験時から合否に関わらず受験することを決めていました、理由は3つあります。
- 実務上の最低かつ妥当レベルであること
- 3級の知識が十分活かせること
- 解答に至るプロセスが面白いこと
選んだ教材とその理由について
- テキスト
LEC出版の「20日で合格る!日商簿記2級最速マスター 工業簿記、商業簿記」を選びました。このテキストを選んだ理由は、20日という明確なペースメーカーがあり、計画を立てやすいと考えたからです。工業簿記が加わり商業も内容が深くなるため、間際に慌てない様に計画的に進められるものを基準にしました。
- 問題集
TAC出版の「日商簿記2級問題演習」を選びました。この問題集を選んだ理由は、謳い文句通り、授業で問題の解き方を教わっている様な解説と量に重点がおかれていたことと、随所にあるワンポイントが解法や電卓の使い方など的確な内容だったからです。2級ともなるとさすがに難しくなるので、疑問点をすぐ解決できる様の解説の充実さにこだわりました。
- 電卓
「Canon LS121TUL」を選びました。この電卓を選んだ理由は、3級受験時から使っており、手になじんでいたからです。
合格にいたる学習プロセス
- 計画(開始時)
テキストの20日(商・工)と問題集の章立てを考慮して、受験日までに日々の目標と月ごとの目標を設定しました。立案の方針は下記の通りです。
- 1週間単位…商業2日、工業2日、復習1日、週末は問題集にあて、1日はその週の遅れた分を取り返す日としました。つまり日々の目標をクリアするとご褒美で休み、クリアできなければ勉強ということになります。
- 1か月単位…4か月でテキストを3回転、残りは問題集の2回転が完了することを念頭においたスケジュールとしました。
- 実行(1か月目~4か月目)
平日は当然まとまった時間はとれないため、テキストの読込みは寝る前でした。その他は隙間時間の利用です。このテキストは、1日単位で基本問題があったので、翌朝に前日の読込んだ箇所とさっと眺め、基本問題を解くというパターンを繰返しました。3級と大きく異なるのは、ボリュームが倍以上になることで、テキストや問題集が厚くなり、持ち歩くのがどうしても億劫になることです。そこで次の工夫をしました。
- 単語カード…今は様々なものが売っており、3級で使ったものより大きめのものを買い、苦手な仕訳や取引を書出しておき、常にポケットに忍ばせては「眺め」ました。
- 演習用紙(裏紙、ルーズリーフ)※画像あり…復習や問題演習でひっかかるところをキーワードや、解法を書き留めておき、必要なものだけ持ち歩き、これも「眺め」ていました。
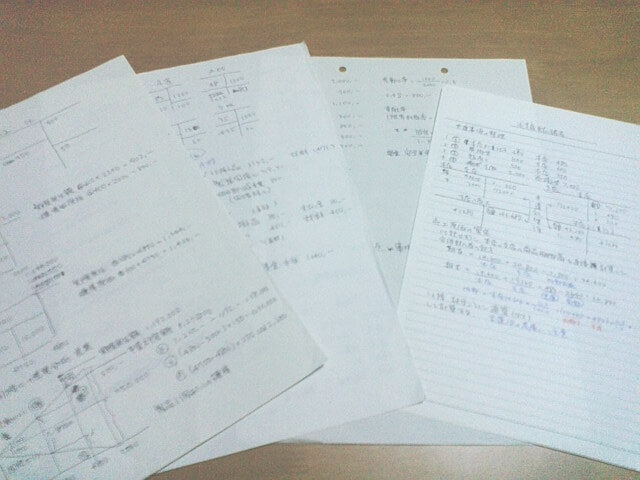
- テスト(4か月目~試験月)
1冊の問題集をマスターするのが王道ということで、実行時に1回終わっているので、この時期に2回転するように配分をしました。全ての問題を均等に行うのは効率が悪いので、理解度のレベルをつけておき、解法が思い浮かばないもの、間違いやすいものを優先しました。
また、今回使った問題集は、1問毎に解答時間があったため、これを意識して解きました。この時も解答は単語カードや演習用紙に書いておき、持ち歩けるようにしていました。
- 仕上げ
このようなプロセスを踏むと、おのずと苦手な分野がわかってきます。これを克服する時期ですが、過去の出題傾向を考慮し、頻度が低かったりするものは思い切って諦める取捨選択も行いました。つまり何度も覚え直し、なかなか身につかないものに時間をかけるより、理解していることの精度を上げる方を優先しました。
また、この簿記検定ナビの仕訳問題対策があることに、この時期に気づき試験当日に全ての問題を解き、総仕上げを行いました。非常にこれは有効でした。知らない勘定科目がでてきましたが、この時期に覚えるべきでないと考え、潔く捨てました。
試験日当日の1日の流れ
- 午前
2級は午後なので、時間的な余裕があったものの、いつも通り6時に起床し、得意分野の問題演習と苦手分野の再チェックを行いました。苦手分野の問題演習は自信喪失につながると思い、眺めてふ~ん、という程度にとどめました。前日の仕訳問題対策で間違えた箇所もチェックしました。
- 午後
30分前に試験会場に到着。余裕のある行動は鉄則です。3級受験時と同様に、単語カード+演習用紙のみ、テキスト類は一切持ち込みませんでした。試験官が入場・説明を聞きながら瞑想し、気持ちを静めました。
試験開始とともに問題をざっと眺め、まずは1問目から入り、時間のかかりそうな3問は飛ばし、5問目に取り掛かりました。2級工業は原価計算がポイントであることを聞いていたので、見た瞬間ニンマリとしましたが、半製品というこれまでのパターンにない算出方法だったので、かなりあせりました。
できるところまで進み、次に移りました。他の問題を解いているうちに、ふと第5問の解法がひらめき、中断して続きをやることにしました。時間のロスであることはわかっていましたが、何かの思し召しと考え、最後まで解くことができました。案の定、時間がなくなり、最後に回した第3問を時間ギリギリまでかかりました。
見直す時間は一切なく、一番点取り問題にしなければならない仕訳で間違いに気づいたものの後の祭りです。全体的には模擬試験よりも手応えはあったので、それ程不安はありませんでした。帰宅後の自己採点では8割とれていましが、やはり一抹の不安は拭えませんでした。
不合格に備え、せっかく覚えたことを忘れないように単語カードなどを時々眺めて、その不安を打ち消す日々が続きました。結果は合格、ホっと胸をなでおろす瞬間でした。
管理人からまー蔵さんへ追加の質問
| 今回、利用された教材や電卓は他の方にもおすすめ出来ますか? | |
| テキストは若干、子供じみた感は否めないものの、学習項目が日単位で分かれており、計画が立てやすかったです。問題集は謳い文句どおり、ワンポイントや解説が充実した上、わかりやすく丁寧です。いずれもオススメできる教材です。
電卓に関しては3級受験時に購入したものを継続利用しました。特に2級だから、といった不便さはありませんでした。 |
| まー蔵さんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |
商業簿記は、精算表です。3級受験時に徹底的に反復練習したことが活かせ、躓くことなく解答できました。一方、工業簿記は標準原価計算です。学生自分から図形問題が好きで、図による解法はスっと入りました。
商業簿記は社債です。償還(満期、買入)の相違による仕訳の違い、満期保有証券の決算がとにかく苦手で何回も間違えました。克服するために、理解することはあきらめ、典型的なパターンのみを繰り返し暗記しました。 |
| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |
| 教材は、決めたものをトコトンやりきることが重要だと思います。巷に出回っている勉強法でも紹介されているように、少しづつでも繰り返すことで定着します。私はこれを「3歩進んで2歩下がる」勉強法と呼んでいます。3日新しいことをやったら、初めの2日分をざっと復習する、これを毎日継続しました。
反省点としては、原価計算などで、解法はあってるのに計算ミスや電卓ミスで数字が異なると、再計算することが多々あったこと。これは非効率ではと今更ながら感じます。適当に切り上げる潔さが必要だったかなぁ。と思います。 |
| 今後は簿記2級をどのように活かす予定ですか?簿記1級・税理士などの上位資格に挑戦される予定はありますか? | |
| 3級から順調にこれたこと、会計学への興味が大きくなったこともあり、折角なので1級に取り組むことにしました。将来税理士にもチャレンジするつもりです。 |
管理人コメント
まー蔵さん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!丁寧に書いていただいたので、とても分かりやすい合格体験記に仕上がっていると思います。
まー蔵さんの勉強方法でぜひ見習っていただきたいのは「決めたものをトコトンやりきる」という点です。独学で勉強していますとどうしても不安になってしまい、いろんな教材に手を伸ばしてしまいがちですが、十分なリサーチをして教材を決めた後は、もう一蓮托生という感じでわき目をふらずに勉強したほうがいいです。
ですから、事前の情報収集にはきちんと時間を割いて、納得のいく教材を探すことが大事になってきます。適当に教材を選ぶのは楽ですし、あれこれ悩んでいる時間はもったいないように感じるかもしれませんが、最初の準備を怠ると後になって響いてきますのでご注意ください。
とても参考になる合格体験記を投稿していただいたまー蔵さんには本当に気持ち程度ですが、amazonのギフト券を送らせていただきます。本当にありがとうございました。
まー蔵さんが使われた教材や電卓のまとめ
- テキスト:20日で合格るぞ!日商簿記2級 光速マスターテキスト(商業簿記・工業簿記)
- 問題集:プラス8点のための問題演習 日商簿記2級
- 電卓:Canon LS121TUL
- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。